~ 相続を“争続”にしないために ~
相続の基礎知識と遺言の上手な活用法
近年の相続問題&相続対策の基本を抑えよう
①超高齢化社会へ突入
②保有財産やライフスタイルの多様化による価値観の変化
③所有財産の多い少ないは関係なく「争続」が年々増加している
④相続税改正により、基礎控除が4割減

①相続人は誰で、財産は何があるのか確認することからスタート
②相続税の対象かどうか?の確認をしましょう
③相続税対策若しくは納税資金の準備
④財産の承継について考える(遺言・民事信託の活用)

相続財産の把握
1. 不動産(土地・建物)
① 登記済権利証 → 登記事項証明書
② 評価証明書 → 役所の固定資産税課
③ 納税通知書など
2.現金・預貯金・有価証券・保険
① 通帳、証書、証券→ 死亡日現在の残高証明書
② 有価証券(株式、公社債、投資信託等)→ 銘柄別の明細書
③ 生命保険・損害保険→ 各種明細書・証明書・計算書など
3. 債務(借入金・未払い金など)
① 金銭消費貸借契約書 → 保証人・連帯保証人の確認
② 返済予定表
③ 未払明細書 → 死亡後に支払った医療費 未納公租公課等
④ 貸地、貸家の敷金・保証金
4.その他
① 貸金庫の有無
② 葬儀費用の明細書、領収書
③ 書画骨董品の明細
④ 手元現金、電話加入権、ゴルフ会員権、家財などの明細
⑤ 給与の明細、退職金、弔慰金の明細
⑥ 相続開始前3年前に贈与された贈与額
⑧ 被相続人の家系図、略歴書
⑨ 遺言書、遺産分割協議書の写しなど
だれが相続人になるのか
① 配偶者
※ 戸籍上の配偶者であって、事実婚は含まれません。
② 下記の順番でいずれか
ⅰ)子
ⅱ)直系尊属 (両親・養親・祖父母)
ⅲ)兄弟姉妹
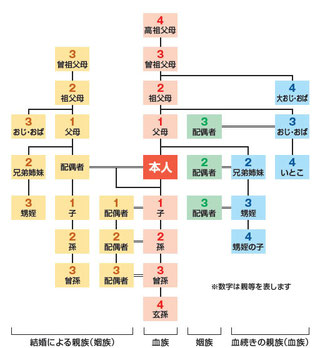
円満な相続のために遺言を活用しましょう!
-
なぜ「遺言」を活用するのか?
-
相続トラブルの主な原因が「遺産分割」にあるからです
相続財産の分割方法
| ① 遺産分割協議 | ② 指定分割 | ③ 調停 |
| 相続人全員の話し合い(合意)により分割 | 遺言により分割内容を指定。
遺産分割協議に優先。 |
遺産分割協議が調わない場合、家庭裁判所に申し立て
※申告期限までに分割協議が調わないと、税務上の |
「争続」にならないために!円満な承継のためには遺言を活用 !
遺言対象者チェックシート
□ 年齢65歳以上
□ 会社、家業、農業経営者
□ 地主、複数の不動産所有者
□ アパート・マンションなどの賃貸物件を所有している
□ 借入金がある
□ 相続税を心配している
□ 財産の大半を配偶者に残したい
□ 妻や子たちの実態に見合った遺産の分け方を決めておきたい
□ 自宅など財産が分けにくい
□ 子のない夫婦
□ 再婚で先妻の子・後妻の子がいる
□ 子供達の仲が悪い
□ 経済的に援助したい子がいる
□ 障害のある子や病弱な家族がいる
□ 配偶者・子がいない
□ 相続人以外の人にも遺産の一部を与えたい
□ 祖先の祭祀の主宰者を指定しておきたい
□ 社会のために寄付をしたい
□ 相続手続につき、妻・子らに負担をかけないよう「遺言執行者」を 指定し、安心しておきたい
遺言の種類
| 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
| 概要 |
公証人役場で、2名の証人の前で遺言内容を公証人に申し述べ、 |
自筆で遺言書を作成。 |
| メリット |
・公文書としての効果を持つ。 |
・手軽でいつでも書くことができる |
| デメリット |
・証人が2名必要 |
・形式不備で法的に無効になりやすい |
遺言の種類
「遺留分」とは・・・一定の相続人には、最低限の相続分として「遺留分」が認められている。(民法第1028条 他)
| 遺留分権利者 | 配偶者・子・父母(兄弟姉妹には遺留分はない) |
| 遺留分減殺請求 |
遺留分が侵害されている場合に、財産を取得した他の相続人に対して遺留分を請求する方法。 |
遺言を書くときは、遺留分に配慮することが必要です!
遺言書作成時のポイント
①可能な限り全ての財産を対象にする。
②遺留分に配慮する。
③不動産の相続は共有は避ける。
④相続税がかかる場合は納税を配慮する。
⑤遺言書の保管を決めておく。
⑥円滑な承継のために遺言執行者を決めておく。
⑦自筆証書より公正証書で作成する。
公正証書遺言作成のスケジュール
① 事前のご相談
(どなたに、何を遺したいのか要望をヒアリングします)
② 遺言公正証書の文案作成
③ 公証役場にて公正証書遺言を作成 ※ここで作成は完了
(証人2名の引き受け)
④ 遺言書正本の保管と管理
⑤ 遺言書の定期的な確認及び変更がある場合は 書き換え
